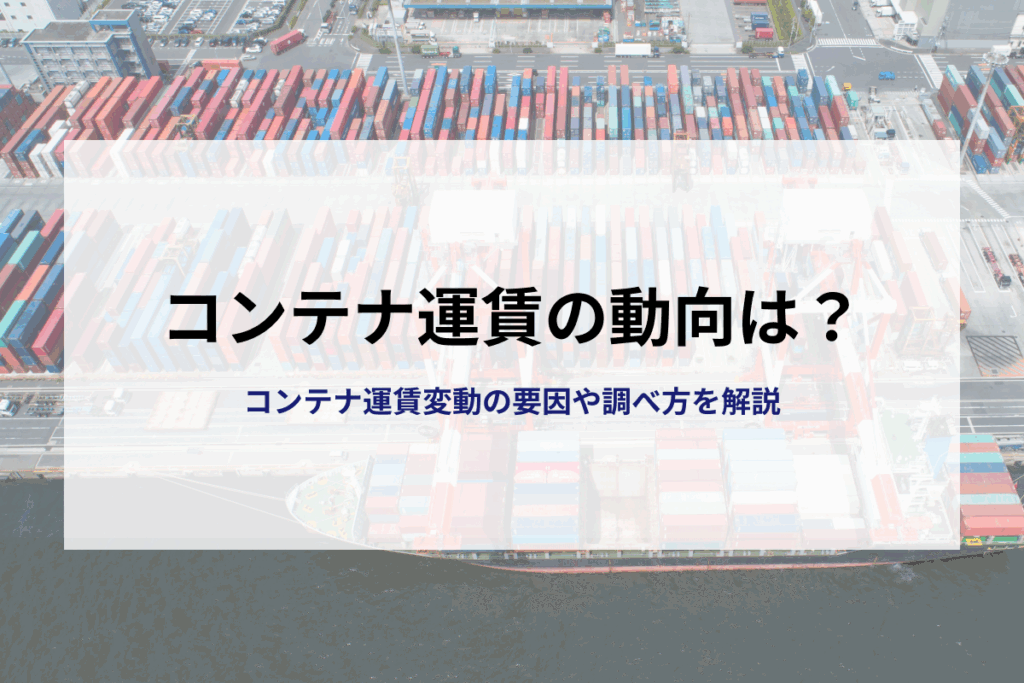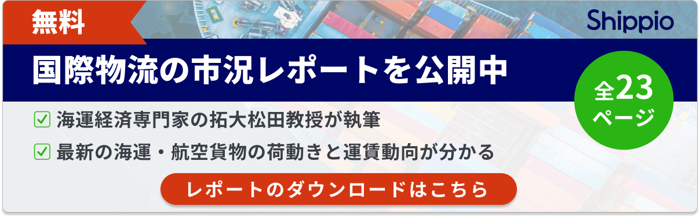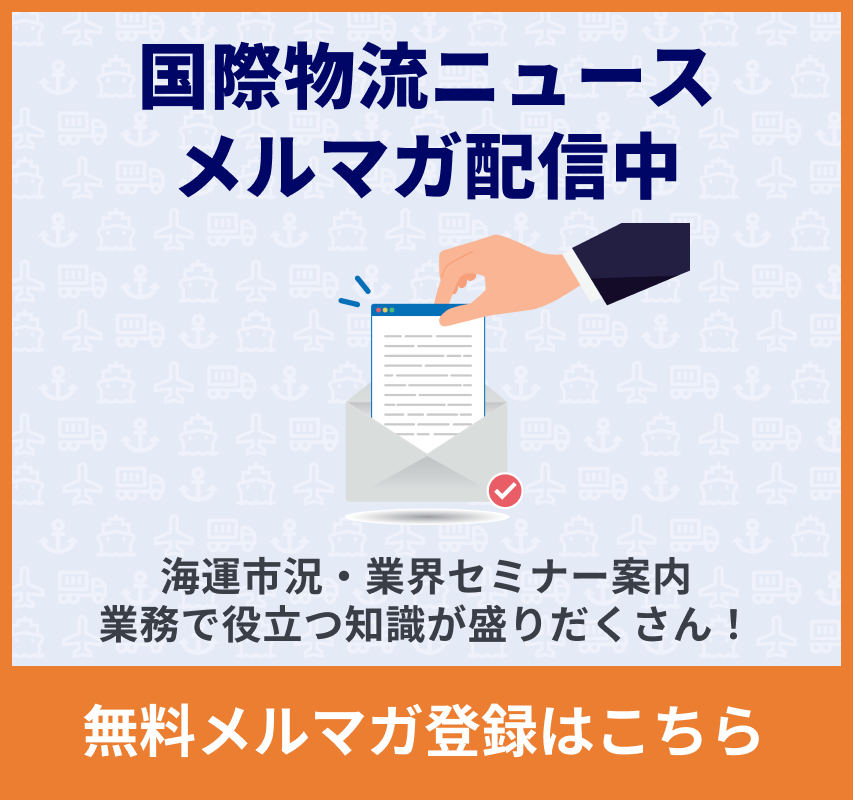新型コロナ禍をきっかけに、国際海上コンテナ輸送の運賃は急激に高騰しました。これに加え、輸送能力の不足や港湾処理能力の低下、運航の遅延が相次ぎ、世界中のサプライチェーンに深刻な混乱をもたらしました。現在でも、地政学的リスクや国際情勢の影響を受け、コンテナ運賃は大きな変動を続けています。
国際海上輸送市場では何が起きているのでしょうか。本記事では、海上運賃の推移やその変動要因、さらには運賃を調べる方法について、わかりやすく解説します。
コンテナ運賃の推移
2020~2021年:コンテナ運賃は右肩上がり
2020年夏以降、コンテナ運賃は急激に上昇し、中国主要港から日本向けの運賃でも同様の高騰が発生しました。この運賃高騰と輸送混乱の背景には、以下の4つの要因があるとされています。
- 米中経済摩擦による新造コンテナ数の減少
2018年からの米中経済摩擦の影響で、世界的に新造コンテナの供給が減少 - 輸出入需要の急増
中国製造業がV字回復し、欧米では巣ごもり需要が増加したことで、輸出入量が増加 - 港湾機能の低下
新型コロナ禍や港湾での労使交渉が原因で、一時的に港湾機能が低下 - コンテナ輸送に必要なリソース不足
コンテナトラックのドライバーやシャーシが不足する傾向が続き、輸送網のひっ迫
さらに、燃料油価格や用船料の上昇に伴う各種サーチャ-ジ(後述)の増加も影響を及ぼしました。加えて、スケジュールの順守率が低下し、運航の遅延が拡大したことで、貨物スペースと空コンテナの慢性的な不足が深刻化しました。
2022年~2023年:コンテナ運賃は後半から下落
2022年初めに、コンテナ運賃は過去最高値を記録し、年央まで高止まりが続きました。しかし、2022年8月頃から中国・上海発の欧米向け運賃が下落し始め、米国西海岸向けの40フィートコンテナ運賃は10月中旬時点で1本あたり2,097ドルまで低下。これは、2月の最高値8,117ドルから約8割もの下落を意味します。
同時に、米国ロサンゼルス港のコンテナ輸入量も新型コロナ以前の水準を割り込み、船会社は予定運行便数の2割以上を減便する対応を余儀なくされました。業界からは「需要の鈍化が予想以上」という声も聞かれ、コンテナ市況は急速に冷え込みました。
運賃下落の主な要因として、以下の3点が挙げられます。
- 景気減速と消費低迷
景気後退懸念による在庫調整やインフレの影響で、消費財の輸送需要が減少 - コンテナ不足の解消
コンテナ供給が改善したことで、逼迫状況が緩和 - 臨時船の追加投入
コンテナ船不足に対応するための臨時船の投入により、輸送キャパシティが増加
2024年:コンテナ運賃の上昇と変動要因
下落傾向にあった海上運賃ですが、2024年1月以降は国際情勢の影響で一時的に上昇しました。紅海危機や東岸でのストライキ、対中関税の強化が輸送環境を混乱させ、スエズ運河の通行を避けるために船舶は喜望峰を迂回するようになったことが要因と考えられます。この結果、輸送時間の延長と供給力の低下が市場に影響を与えました。
一方で、eコマースの需要増加や企業の在庫補充によって、主要な輸送航路で予想を超える需要が発生しました。アジア太平洋地域の船舶利用率は100%以上に達し、運送業者は高収益貨物を優先する動きが見られました。
さらに、ストライキの懸念やピークシーズンサーチャージ(PSS)の導入予定など、需給の不均衡は運賃変動を引き起こしています。新造船の投入により供給力は一部強化されましたが、地政学的リスクの影響で完全には解消されていません。
貿易を事業の中心とする荷主にとって、コンテナ運賃の大きな変動は課題となっています。しかし、このような状況下だからこそ、コンテナ輸送の特徴を正確に理解し、自社のニーズに合った最適な輸送形態を選択することが一層重要となっています。
コンテナ運賃を構成する3つの主な要素
国際海上コンテナ輸送の運賃は、海運同盟が設定する協定運賃を基に、基本運賃(ベースレート)、割増運賃(サーチャージ)、地域独自のチャージなどで構成されています。同一航路内での競争を抑えるため、この運賃体系は特例として認められています。それぞれの要素について以下に説明します。
1.基本運賃(ベースレート、オーシャンフレート)
基本運賃は、輸送の土台となる料金で、品目別運賃と品目無差別運賃の2種類があります。
品目別運賃
貨物の種類や形状、包装状態などによって運賃が異なり、以下の基準で算出されます。
- 容積建て
貨物の容積を基準に運賃を計算。フレートトン(1.133立方メートルまたは1,000kgのいずれか大きい数値)を基準とします。 - 重量建て
重量を基準に計算。容積が小さくても重量がある貨物に適用され、フレートトンを基準とします。 - 従価建て
高価な貨物(貴金属や高付加価値品)に適用され、貨物の価格に一定割合を掛けて運賃を設定します。
品目無差別運賃
貨物の種類を問わず、コンテナ単位で設定される運賃です。「ボックスレート」として知られ、コンテナ1本あたりの料金で計算されます。
2.割増運賃(サーチャージ)
基本運賃に追加される料金で、運送状況やコストに応じて設定されます。主な割増料金は以下の通りです。
- 燃料価格の変動によるサーチャージ(BAF: 燃料費調整係数)
燃料価格の変動に応じて調整されるサーチャージ。航路により異なる名称(例:BS、EBS)で設定されますが、基本はトンまたはコンテナ単位で設定されます。 - 為替レートの変動によるサーチャージ(CAF: 通貨変動調整係数)
為替レートの変動に対応するサーチャージ。日本円高騰時には「YAS(円高損失補填料金)」が適用される場合もあります。 - 貨物取扱関連のサーチャージ(THC/CHC: コンテナヤード利用料金)
コンテナヤードの利用料金で、フルコンテナ(FCL)と少量貨物(LCL)で異なる名称が用いられます。 - その他の割増料金
季節的需要増加時の「ピークシーズンサーチャージ(PSS)」や、特定港の混雑による「混雑割増料金(Congestion Surcharge)」、書類作成手数料(D/O Fee, DOC Fee)など、状況に応じた割増料金が加算されます。
地域独自のチャージ
航路や地域ごとに特有の追加料金が発生します。以下は代表的な例です。
- 中国航路
・ SPS(上海港を使用する場合にかかるチャージ)
・ CRS(日本から積載し、中国向けの輸送の際にかかるチャージ)
・ CRC(香港から積載し、アジア域内に輸送する際の運賃にかかるチャージ)
・ DCF(書類作成する際にかかる費用)
・ System Charge(中国発のフォワーダー扱い時に発生することが多い)
- 台湾
・ KAC(基隆港から輸出する貨物にかかるチャージ)
- 韓国
・ CNTR TAX(韓国から輸出する際のコンテナへの税金)
・ Wharfage(埠頭の使用料) - 北米
・ SPSC(北米向け輸送の海上運賃に適用される夏季限定チャージ)
・ AMS(北米、EU向けの船積みに適用。24時間ルール対応の手続きのためのチャージ) - 運河通行料金
その他にも、運河を通行する航路を利用する際にかかるチャージもあります。
・ STF(スエズ運河の通過にかかるチャージ)
・ PCS(パナマ運河の通行にかかるチャージ)
このように、国や航路ごとにさまざまなチャージが設定されているため、詳細を正確に把握するにはフォワーダーに相談し、詳細を確認することが重要です。
コンテナ運賃を調べる
フォワーダーに輸送を依頼する際、見積もりの妥当性を確認したり、値段交渉を行ったりするためには、コンテナ運賃の相場を自ら把握しておくことが重要です。
コンテナ運賃を調べるには、船会社、フォワーダー、輸送コンサルタント会社などが提供するオンライン検索等の利用が手軽で有効な手段です。
自ら運賃を調べて相場を把握することで、フォワーダーから提示された見積もりの妥当性を判断できるだけでなく、価格交渉の際の有力な材料となります。また、異なるサービスプロバイダーを比較することで、コストパフォーマンスの高い輸送手段を選ぶことが可能になります。
Shippioなら簡単にお見積りを提供
Shippioは、日本初のデジタルフォワーダーとして、従来の海上輸送・航空輸送・通関手配・陸送手配などのフォワーディングサービスに加え、顧客の貿易業務を効率化するクラウドサービスを提供しています。
Shippioのクラウドサービスを利用することで、輸送条件を入力するだけで、迅速に輸送コストやスケジュールを含む見積もりを取得できます。また、関係者全員が最新情報にアクセスできるため、社内のコミュニケーションコストの削減や業務のスピードアップが期待できます。さらに、Shippioは荷主向け貿易業務SaaS「Any Cargo」を提供しており、他社フォワーディング案件も含めた貿易業務の一元管理が可能です。 これにより、貿易業務全体の効率化と可視化が実現します。
Shippioのサービスは、貿易業務のデジタル化と効率化を推進し、国際物流のDXを支援します。
コンテナ運賃目安は「Freightos」で入手
Freightos社が提供する「Freight Calculator」を利用すれば、無料でコンテナ運賃の目安を入手することができます。出発地港、到着地港、貨物サイズ、パレット数、重量などを入力するだけで、海上輸送運賃の概算額(サーチャージなどは含まない)を確認できます。これにより、運賃相場の変動把握や運送手段の選定に役立てることが可能です。ただし、日本語版は提供されていない点にご注意ください。
また、公益財団法人日本海事センターのウェブサイトでは、主要航路のコンテナ運賃動向を確認できます。こちらはPDF形式で提供されており、大まかな運賃を把握するのに便利です。さらに、JETROの「投資関連コスト比較調査」サイトでも海上コンテナ輸送費の概算額が参照可能でしたが、現在は運賃の変動が大きいことから調査対象外となっています。
なお、オンラインツールで得られるのはあくまで目安であり、確定した運賃や燃料サーチャージなどの詳細費用については、必ずフォワーダーから見積を取得してください。その上で、輸送の納期や品質を考慮して適切な判断を行うことをお勧めします。
コンテナの運賃の動向と運賃変動の要因、調べ方
本記事では、直近の運賃推移、運賃変動の要因、運賃の調べ方について解説しました。
サプライチェーンの混乱を経て、現在もコンテナ運賃はさまざまな要因により日々変動しています。この記事でご紹介した運賃変動の要因や調べ方が、業務における迅速な運賃動向の把握に役立つきっかけとなれば幸いです。
さらに、最新の海上運賃や航空運賃の動向については、以下の市況レポートで随時更新されていますので、ぜひご活用ください。