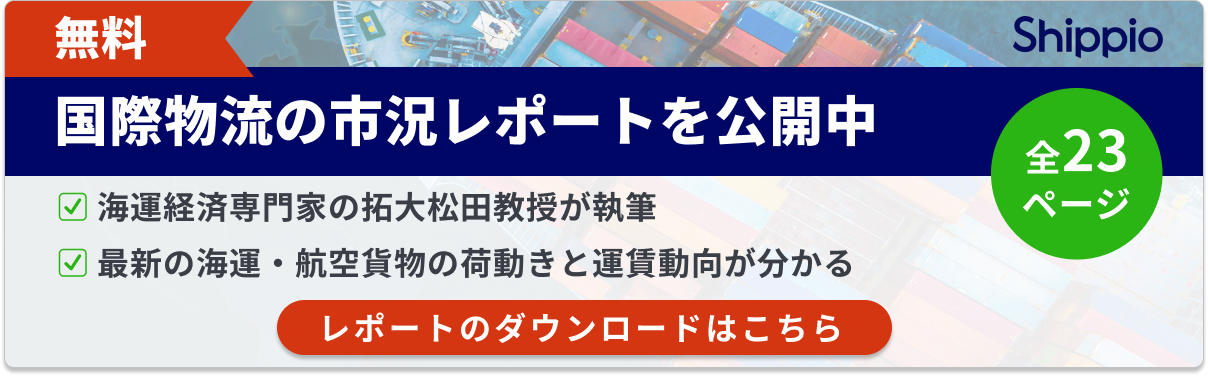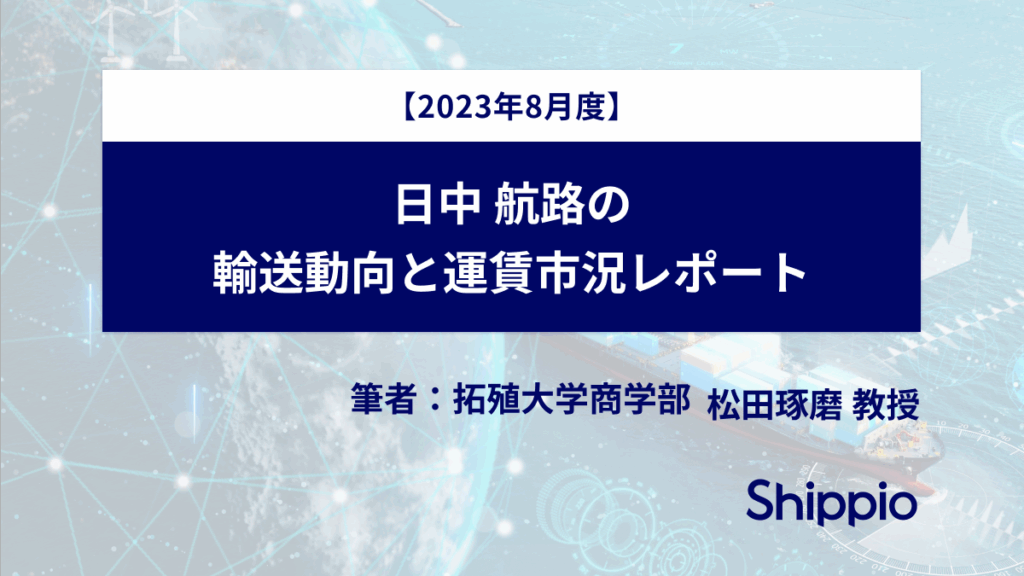
筆者:松田琢磨(拓殖大学 商学部 国際ビジネス学科 教授)
※こちらは【2023年8 月時】のレポートです。最新版の市況レポートは以下からアクセスできます。
目次
A. はじめに
1.筆者について
B. 日中航路の輸送動向の現状
1.主な輸送品目の動向
2.海上輸送サービスの動向
C. 日中航路の市況状況
はじめに
筆者について
拓殖大学商学部教授.筑波大学第三学群社会工学類卒業,東京工業大学大学院理工学研究科博士課程単位取得退学,博士(学術)(東京工業大学).2011年より(公財)日本海事センター研究員,2018年同主任研究員.同センターでは主にコンテナ輸送に関する調査,分析に従事.2020年より現職.2023年4月より拓殖大学商学部国際ビジネス学科長.研究分野は海運経済学,コンテナ輸送,国際物流など.2014年度日本海運経済学会賞(論文の部),2014年度および2020年度日本物流学会賞(論文等の部),2021年度日本海運経済学会国際交流賞をそれぞれ受賞.近著に『新国際物流論 基礎からDXまで』(共著,2022年),『日の丸コンテナ会社ONEはなぜ成功したのか?』(共著,2023年),『コンテナから読む世界経済 経済の血液はこの「箱」が運んでいる!』(2023年)がある.所属学会は日本海運経済学会(常任理事,産官学連携委員長,編集副委員長),日本物流学会(理事,編集委員)など.2021年5月よりNewsPicksプロピッカーも務め,海運・物流のニュースを中心にコメントしている.
日中航路の輸送動向の現状
日本にとって中国は最大の貿易相手国であり,2022年における貿易額は輸出19.0兆円,輸入24.8兆円に上り,全世界の20.3%を占めています.コンテナ輸送においてはさらにその存在は大きく,金額ベースで輸出入額27.7兆円で33.1%,TEUベース(2021年)では40.5%と大きな位置を占めています.このレポートでは,日中航路の荷動きと運賃,配船動向に関するデータを示し,市場動向について概説します.合わせて,航空輸送の動向についても簡単に触れることとします.
金額ベースで見ると海上コンテナ輸送は輸出では61.2%,輸入では73.5%を占めています.この比率は輸出では10%近く減少している一方で,輸入では少しの減少にとどまっています.
1. 主な輸送品目の動向
a. 海上コンテナ輸送
財務省貿易統計によると,2022年には海上コンテナを利用して日本から中国へ10.0兆円の輸出が行われました(表1参照).前年比では4.2%増でした.
表1で示しているのは日本から中国への主な輸送品目です.第一位の段ボール原紙・包装紙は,この数年で急速に輸出量を増やしている品目です.この品目は様々な商品の包装に用いられる段ボールの原料となります.2017年以降,中国は環境規制のため古紙など固形廃棄物の輸入が制限されるようになり,古紙と廃プラスチックが多くを占めた日本からのコンテナ貨物輸出は大きく減少しました.
その一方,中国で古紙が足りなくなったことで,段ボール原紙の生産に支障が出るようになりました.中国の加工会社は海外から段ボール原紙を輸入することで対応し,これが日本からの輸出を増やしています.日本から見ると,これまで輸出してきた古紙を日本側で処理してから輸出していることになります.
そのほか,自動車部品を除くと上位品目に原材料が多くみられていることが特徴です.
表1:日本から中国へのコンテナ輸送による主な輸出品目(2022年)
| HS番号 | 品目名 | 輸出量 (トン) | 輸出額 (億円) | |
| 1 | ‘4805 | 段ボール原紙・包装紙など | 501,846 | 346.2 |
| 2 | ‘3901 | エチレンの重合体(一次製品) | 387,297 | 732.5 |
| 3 | ‘3907 | ポリアセタールその他のポリエーテル,エポキシ樹脂及びポリカーボネート,アルキド樹脂,ポリアリルエステルその他のポリエステル(一次製品) | 329,878 | 522.2 |
| 4 | ‘3902 | プロピレンその他のオレフィンの重合体(一次製品) | 305,770 | 5,864.9 |
| 5 | ‘8708 | 自動車部品,付属品 | 288,741 | 1,382.4 |
| 6 | ‘7403 | 精製銅又は銅合金の塊 | 232,260 | 2,306.9 |
| 7 | ‘3920 | プラスチック製のその他の板,シート,フィルム,はく及びストリップ | 226,659 | 2,547.8 |
| 8 | ‘7404 | 銅のくず | 191,462 | 380.4 |
| 9 | ‘3824 | 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む.)において生産される化学品及び調製品 | 182,044 | 865.8 |
| 10 | ‘4002 | 合成ゴム,油から製造したファクチス及び天然ゴム類との混合物(一次製品,板,シート又はストリップの形状) | 174,227 | 2,267.7 |
| 輸出額合計 | 99,838.8 |
データ出所:財務省「貿易統計」
2022年には海上コンテナを利用して日本から中国へ17.7兆円の輸出が行われました(表2参照).前年比では25.8%増でした.2010年と比較して,日本からのコンテナ貨物の輸出額は7.9兆円,80.0%の増加を見せています.重量ベースでは同じ期間で72.9万トン,3.4%の増加でした.
表2で示しているのは中国から日本への主な輸送品目です.第一位の昇降機,クレーンそのほか機械向けの部分品や第三位の自動車部品といった機械類のほか,第二位の家具類や第九位の腰掛け及びその部分品(椅子類),第18位の寝具類といったインテリア品のほか,輸出に比べると商品や製品の貿易が多く行われていることがわかります.鉄鋼やプラスチックについても原料ではなく製品が輸送される傾向にあります.
また,食品や加工食品の輸入が多くみられることも特徴です.
そのほか,マスクが上位品目にあります.2022年度において不織布マスクは85.3億枚生産されましたが,そのうち62.5億枚が輸入されており,この多くを中国産のマスクが占めています.マスクの着用が減っているため,マスクの輸入量は今後減ってくる可能性が高いものの,一定量の輸入は続くとみられます.
表2:中国からのコンテナ輸送での主な輸入品目(2022年)
| HS番号 | 品目名 | 輸入量 (トン) | 輸入額 (億円) | |
| 1 | ‘8431 | 昇降機,クレーンそのほか機械向けの部分品 | 721,997 | 2,417.5 |
| 2 | ‘9403 | 家具類及び部分品 | 511,854 | 2,054.2 |
| 3 | ‘8708 | 自動車部品,付属品 | 421,406 | 4,040.5 |
| 4 | ‘0710 | 冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る.) | 394,802 | 870.1 |
| 5 | ‘7326 | その他の鉄鋼製品 | 389,691 | 1,411.0 |
| 6 | ‘3926 | その他のプラスチック製品 | 338,053 | 2,568.6 |
| 7 | ‘0703 | たまねぎ,エシャロット,にんにく,リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る.) | 322,613 | 361.2 |
| 8 | ‘7308 | 構造物及びその部分品並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板,棒,形材,管その他これらに類する物品 | 314,955 | 893.2 |
| 9 | ‘9401 | 腰掛け及びその部分品 | 290,504 | 2,388.3 |
| 10 | ‘3923 | プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓,ふた,キャップその他これらに類する物品 | 252,007 | 1,194.4 |
| 輸入額合計 | 177,210.6 |
データ出所:財務省「貿易統計」
図1で示しているのは日中航路における海上輸送コンテナ貨物輸送量の推移です.日本から中国への日中往航コンテナ輸送量は年々減少を続けており,2022年の輸送量は859.9万トンで2010年に比べて481.0万トン,35.9%少なくなっています.金額ベースでは2022年において2010年比で38.2%の増加となっています.金額ベースの増加には,同じ時期の人民元/円の為替レートの減価,すなわち円の対人民元レートが円安に振れていることがあるとみられます.2010年から2022年の間に円と人民元の為替レートは13.0円/人民元から19.5円/人民元,50.4%の減価がみられています.
一方で中国から日本への日中復航荷動き量は大きな変動はなく,増加トレンドも減少トレンドも見られていません.2022年の輸送量は2160.1万トンで2010年に比べて72.9万トン,3.5%増加しています.その結果,復航輸送量に対する往航輸送量の比率であるインバランスは2010年の64.0%から24.3%ポイント下落の39.7%と拡大し,空コンテナ輸送の問題が大きくなっています.
2010年と比較して,日本からのコンテナ貨物の輸出額は2.8兆円,38.2%の増加を見せています.一方,重量ベースでは同じ期間で481万トン,35.8%の減少です.
b. 航空輸送
2022年には航空輸送を利用して日本から中国へ6.3兆円の輸出が行われました(表3参照).前年比では25.8%増でした.輸出額のうち,44.5%分が成田税関で,24.6%分が関西国際空港税関で通関が行われており,これらの空港から多くが輸出されていることがわかります.
表3で示しているのは日本から中国へ航空機を使って運ばれた主な輸送品目です.第一位の集積回路や第二位の半導体ボール,ウエハーや第三位の半導体デバイスといった半導体関連の品目のほか,第四位のコンデンサーや第五位の接続子など半導体関連や精密機器の貿易が多く行われていることがわかります.比較的小さく,付加価値の高いものが航空貨物輸送されています.表3で示される品目で輸出額の48.0%を占めています.
表3:日本からの航空輸送による主な中国向け輸出品目(2022年)
| HS番号 | 品目名 | 単位 | 輸出量 (トン) | 輸出額 (億円) | |
| 1 | ‘8542 | 集積回路 | NO | 23,505,247,955 | 9,400.0 |
| KG | 930,342 | 578.9 | |||
| 2 | ‘8486 | 半導体ボール,半導体ウエハー,半導体デバイス,集積回路又はフラットパネルディスプレイの製造に専ら又は主として使用する機器など | KG | 13,786,232 | 5,509.7 |
| 3 | ‘8541 | 半導体デバイス,光電性半導体デバイス,発光ダイオード(LED)及び圧電結晶素子 | NO | 17,397,423,282 | 2,304.9 |
| TH | 28,174,771 | 482.3 | |||
| KG | 285,332 | 119.8 | |||
| 4 | ‘8532 | 固定式,可変式又は半固定式のコンデンサー | KG | 3,021,538 | 2,246.8 |
| 5 | ‘8536 | 電気回路の開閉用,保護用又は接続用の機器並びに光ファイバー用又は光ファイバーケーブル用の接続子 | KG | 4,927,903 | 1,566.8 |
| 6 | ‘8524 | フラットパネルディスプレイモジュール | KG | 7,120,548 | 1,373.5 |
| 7 | ‘8534 | 印刷回路 | KG | 973,757 | 1,099.9 |
| 8 | ‘9001 | 光ファイバー,光ファイバーケーブル,偏光材料製のシート及び板並びにレンズ(コンタクトレンズを含む.),プリズム,鏡その他の光学用品 | KG | 2,921,614 | 1,052.6 |
| NO | 3,131,179 | 45.2 | |||
| 9 | ‘3818 | 元素を電子工業用にドープ処理したもの及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの | KG | 972,241 | 988.1 |
| 10 | ‘8543 | 電気機器(信号発生器など) | NO | 804,277,592 | 879.6 |
| KG | 93,130 | 191.4 | |||
| 輸出額合計 | 63,220.9 |
注:単位のNOは「個」,THは「千個」を意味しています.
データ出所:財務省「貿易統計」
2022年には航空輸送を利用して中国から日本へ6.4兆円の輸出が行われました(表4参照).前年比では12.7%増でした.輸入額のうち,70.8%分が成田税関で,18.9%分が関西国際空港税関で通関が行われており,これらの空港から多くが輸出されていることがわかります.
表4で示しているのは中国から日本へ航空機を使って運ばれた主な輸送品目です.第一位の電話機(主にスマートフォン)や第二位のコンピュータ(パソコン類),第三位の集積回路などがあります.第八位のテレビカメラ,デジタルカメラや第十位のマイク,ヘッドホンやイヤホンなど輸出に比べると完成品や最終製品が多くみられています.また,コロナウイルスの抗体検査で使われる検査キットといったものも航空輸送で輸入されていることがわかります.表4で示される品目で輸出額の72.6%を占めています.
表4:航空輸送による中国からの主な輸入品目(2022年)
| HS番号 | 品目名 | 単位 | 輸入量 (トン) | 輸入額 (億円) | |
| 1 | ‘8517 | 電話機(スマートフォン及び携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話を含む.)及びその他の機器 | NO | 60,631,303 | 23,367.6 |
| KG | 1,162,435 | 744.3 | |||
| 2 | ‘8471 | 自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機,データをデータ媒体に符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械(パソコンなど) | NO | 23,549,560 | 10,823.2 |
| 3 | ‘8542 | 集積回路 | NO | 3,130,753,436 | 3,372.2 |
| KG | 49,825 | 21.9 | |||
| 4 | ‘8473 | パソコンなどに利用する部分品,付属品 | KG | 3,965,464 | 1,091.0 |
| 5 | ‘8541 | 半導体デバイス,光電性半導体デバイス,発光ダイオード(LED)及び圧電結晶素子 | NO | 13,732,849,075 | 935.5 |
| KG | 115,615 | 18.3 | |||
| 6 | ‘8536 | 電気回路の開閉用,保護用又は接続用の機器並びに光ファイバー用又は光ファイバーケーブル用の接続子 | KG | 5,840,442 | 931.1 |
| 7 | ‘3822 | 診断用又は理化学用の試薬及び診断用又は理化学用の調製試薬並びに認証標準物質 (コロナなどの検査キットもこの分類) | KG | 3,681,872 | 861.9 |
| 8 | ‘8525 | ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器,テレビジョンカメラ,デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー | KG | 1,854,217 | 839.6 |
| 9 | ‘8504 | トランスフォーマー,スタティックコンバーター(例えば,整流器)及びインダクター | KG | 7,804,548 | 823.0 |
| 10 | ‘8518 | マイクロホン及びそのスタンド,拡声器,へッドホン及びイヤホン,マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの,可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置 | KG | 2,039,858 | 691.9 |
| 輸入額合計 | 63,905.9 |
注:単位のNOは「個」を意味しています.
データ出所:財務省「貿易統計」
図2で示しているのは日本・中国間における航空貨物の輸出入額の推移です.日本から中国への航空貨物での輸出額は年々増加を続け,2010年と比較して,日本からの航空貨物の輸出額は2.8兆円,81.9%のプラスとなっています.中国から日本への航空貨物輸入額も同様に増えており,2010年と比較して,日本からの航空貨物の輸入額は3.2兆円,106.3%の増加でした.航空輸送では海上コンテナ輸送で拡大しているインバランス問題はみられていません.
2. 海上輸送サービスの動向
表5は2022年における日中航路の中国側発着地と週当たりスペースです.日中航路では北から華北,華東,華南の地域に向けたサービスが分かれて提供されています.華北は天津新港,大連,青島など山東省より北の地域で,華東は江蘇省から浙江省の地域,上海や寧波舟山港が含まれています.華南は福建省から広東省,海南省の地域で厦門,広州,深圳が含まれます(図3参照).
表5:日中航路の中国側発着地と週当たりスペース
| 方面 | サービス数 | うち東南アジア諸国 寄港サービス | 週当たりスペース(TEU) |
| 華東 | 55 | 1 | 45,323 |
| 華東/華南 | 2 | 2 | 3,491 |
| 華南 | 33 | 32 | 53,394 |
| 華南/華東/華北 | 1 | 1 | 1,017 |
| 華北 | 39 | 0 | 28,415 |
| 華北/華東 | 3 | 0 | 3,062 |
| 総計 | 133 | 36 | 134,701 |
注:東南アジア,他地域に割り当てられているスペースも含む
注:華北は山東省より北,華東は浙江省より北,華南は福建省より南
データ出所:オーシャンコマース『国際輸送ハンドブック2022』より作成
上海,寧波を擁する華東地域向けには55のサービスがあり,週当たり4.5万TEU程度のスペースが提供されています.この地域には太倉港向けのRORO船の航路もあり,アパレル製品などの輸送にも利用されています.
華北地域向けは華東地域向けに比べサービスの数も少なく,サービスあたりのスペースも小さくなっています.これは華北向けのサービスが比較的小さい船で提供されていることを意味しています.週当たりで約2.8万TEUのスペースが提供されています.
華南地域向けは週当たり提供スペースが5.3万TEUと最も大きくなっているものの,これらの港へはベトナムやシンガポールなど東南アジアや台湾向けの航路が寄港することが一般的になっているためです.
表6は2022年における日中航路の日本側発着地と週当たりスペースです.京浜港と名古屋港を含む東日本,阪神港を含む西日本向けのサービスが大半を占めるものの,九州地域発着や日本海発着といった地方港のみ寄港のサービスも提供されています.成田空港や関西国際空港への集中度が高い航空貨物輸送に比べると地方への輸送が確保されていることがわかります.
表6:日中航路の日本側発着地と週当たりスペース
| 方面 | サービス数 | 地方港のみ寄港 (京浜,阪神,名古屋除く) | 週当たりスペース(TEU) |
| 九州 | 12 | 12 | 7,011 |
| 西日本 | 24 | 5 | 18,650 |
| 西日本/九州 | 9 | 1 | 11,108 |
| 東日本 | 37 | 2 | 43,458 |
| 東日本/九州 | 6 | 4 | 4,461 |
| 東日本/西日本 | 29 | 0 | 41,985 |
| 東日本/西日本/九州 | 2 | 0 | 1,254 |
| 東日本/日本海 | 2 | 2 | 975 |
| 日本海 | 10 | 10 | 4,808 |
| 日本海/九州 | 2 | 2 | 992 |
| 総計 | 133 | 37 | 134,701 |
注:西日本は和歌山県より西,東日本は三重県より東,下関港は九州に含めている
データ出所:オーシャンコマース『国際輸送ハンドブック2022』より作成
表7は,表5および表6に示される日中航路サービスをに参入している船社の一覧です.日中航路では,近距離を中心とする中国や韓国,台湾の近海船社やマースクの子会社であるシーランドアジアなども参入しています.日本の海運会社ではツネイシホールディングス傘下のコンテナ海運会社である神原汽船が西日本や日本海から華北・華東向けのサービスを提供しています.基幹航路にもサービスを提供する船社のうち,COSCOは華北や華東向けにもサービスを提供している一方,OOCL,エバーグリーンといった船社は,東南アジアや台湾への寄港を行うサービスで華南地域の港に寄っています.
表7:日中航路の主な運航船社
| 運航船社 | サービス数 | 週当たりスペース (TEU) | 比率 |
| SITC | 17 | 16,184 | 12.0% |
| ワンハイ(台湾) | 9 | 12,922 | 9.6% |
| OOCL(香港) | 4 | 12,361 | 9.2% |
| COSCO | 11 | 11,215 | 8.3% |
| エバーグリーン(台湾) | 5 | 10,319 | 7.7% |
| 上海錦江航運 | 11 | 9,896 | 7.3% |
| シノトランス | 11 | 9,390 | 7.0% |
| インターエイシア(台湾) | 5 | 5,736 | 4.3% |
| T.S. Lines(香港) | 5 | 5,320 | 3.9% |
| HASCO | 5 | 4,708 | 3.5% |
| KMTC(韓国) | 8 | 3,753 | 2.8% |
| シーランドアジア(マースク) | 1 | 3,643 | 2.7% |
| 太倉港集装箱海運有限公司 | 4 | 3,420 | 2.5% |
| 神原汽船(日本) | 4 | 3,294 | 2.4% |
| その他 | 33 | 22,539 | 16.7% |
| 総計 | 133 | 134,701 | 100.0% |
注:東南アジア,他地域に割り当てられているスペースも含む
注:華北は山東省より北,華東は浙江省より北,華南は福建省より南
データ出所:オーシャンコマース『国際輸送ハンドブック2022』より作成
日中航路の市況動向
a.海上コンテナ輸送
2023年7月時点で,日本から中国各地へのコンテナ輸送サービスの運賃は天津(華北地域)向けが790ドル/FEU,上海(華東地域)向けが470ドル/FEU,塩田(華南地域)向けが800ドル/FEU,香港向けが900ドル/FEUとなっています(図4参照).全体として航路ごとに大きな差はみられていませんが,直近では上海向けの運賃が低めに推移しています.
日本発のコンテナ航路は荷物の少ない帰り方面(Backhaul)であるため,運賃水準は中国発より低く,変動も比較的大きくありませんでした.それでもサプライチェーンの混乱期にはコロナ前の約2倍の水準まで運賃は上昇していました.明確に運賃が下落に転じたのは2022年後半のことであり,下落傾向は現時点でも続いています.現在の水準はコロナ前と変わらないか,それより低い水準となっています.
2023年7月時点で,中国各地から日本へのコンテナ輸送サービスの運賃は天津発が910ドル/FEU,上海発が1,260ドル/FEU,塩田発が970ドル/FEU,香港発が880ドル/FEUとなっています(図5参照).サプライチェーンの混乱期を除くと,やはり全体として航路ごとに大きな差はみられていません.サプライチェーンの混乱期は華南地域発の運賃の上昇が高かったことがわかります.
サプライチェーンの混乱期における運賃変動も,基幹航路に比べると比較的大きくなくコロナ前の約2~3倍の水準まで運賃が上昇していました.運賃が下落に転じたのは2022年5~7月のことであり,往航同様,現時点に至るまで下落傾向が続いています.直近では上海発の航路の運賃がほかの地域よりも高めかつ運賃下落も緩やかです.横浜→上海間の運賃が低いことと合わせて考えると,上海からの輸送量は一定程度ある一方で日本からの輸送量が追いついていないことが示唆されます.
b.航空輸送
Freightos社の発表によると、2023年7月18日の日本―中国の航空貨物運賃は日本発が906円/kg、中国発が1007円/kgとなっています(図6および7参照)となりました.コロナ禍におけるサプライチェーンのひっ迫状況が緩和されつつあることにともなって世界では需給の緩和に沿って運賃も下落傾向にあります.直近では日中間の航空輸送運賃は1000円/kg前後で落ち着く展開となっています.
c.まとめ
日中コンテナ航路は日本と中国の間の貿易を担う重要な航路です.コンテナ貨物は日本発が主に原材料,中国発が半製品や最終製品,食品などを中心に輸送している.一方,航空貨物輸送では半導体や精密機器を中心に輸送しており,両社間で輸送品目の競合は少ない傾向にあります.2017年の環境規制後,日本から輸出する貨物が減り気味であり,日本発と中国発の貨物量の格差(インバランス)が拡大傾向にある.航空貨物輸送ではインバランスはあまりみられませんでした.
一方,かつてゼロ運賃が横行するなど,日中コンテナ航路は従来から参入船社間の競争の激しい航路です.現在もグローバルアライアンスに参加するような大規模船社だけでなく,域内輸送を中心とする近海船社が輸送の多くを担っています.また,距離が短いため,航空輸送による時間短縮効果が小さく,コンテナ輸送と航空輸送の間での潜在的な競合関係は強い傾向にあります.競争が激しいことは,コロナ禍の時期のサプライチェーンの混乱期に際して運賃の上昇幅が基幹航路より小さかったことにも表れています.
コンテナ輸送の運賃はコロナ前の水準へと戻っており,航空輸送運賃も直近では大きな変化はみられていません.ニアショアリングやチャイナプラスワンが進行する傾向にあるうえ,中国の経済見通しが弱含みであることも考えると,荷動きに大きな変動があるとは見られにくく,スペースに余裕があると考えられるため当面はいずれも運賃が大きく上がるのは難しい状況と考えられます.
※こちらは【2023年8 月時】のレポートです。最新版の市況レポートは以下からアクセスできます。